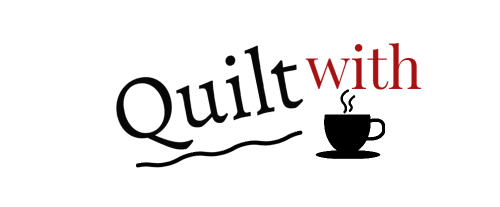今回は、ゲーム実況やライブ配信に欠かせない、キャプチャボードの選び方について深掘りしてみます。
キャプチャボードはゲーム実況やライブ配信に欠かせない機器です。いろいろな種類があるため、自分の目的や予算に合わせて最適な製品を選ぶ必要があります。
今回は選び方のヒントとなる情報として、キャプチャボードの概要、歴史と進化、主な用途、選ぶポイントなどを解説します。
キャプチャボードの概要
キャプチャボードとは、ビデオやオーディオの信号をパソコンに取り込むための装置のことを指します。映像や音声をデジタル化する役割を果たしています。そのため、ゲーム機やカメラから出力される映像を録画したり、ライブ配信したりするのに役立つんです。
またデジタル信号だけでなく、アナログ信号にも対応しています。つまり、HDMIやDVIといったデジタル信号はもちろん、コンポジットやS端子などのアナログ信号も取り扱えるんですね。
内蔵型と外付け型、それぞれの特徴
キャプチャボードは、大きく「内蔵型」と「外付け型」の二つのバリエーションに分けられます。内蔵型は、直接パソコンの拡張スロットに装着する形式で、これにより高解像度の画像や低遅延といった利点を享受することが可能です。外付け型はUSBやThunderbolt等の接続ポートを介してパソコンに繋げる形式で、取り外したり持ち運んだりするのが容易という特性があります。
また内蔵型は、パソコンの本体内に直接装着するストレージデバイスです。外付け型は、USBケーブル等を使ってパソコンと連携するストレージデバイスです。
内蔵型のメリットとしては、データの高速な転送が可能なこと、電源供給を別途必要としないこと、そして、本体内に収納されるためスペースを占有しないことが挙げられます。デメリットは、装着や交換が一筋縄ではいかないこと、パソコン本体の故障や盗難によりデータが失われるリスクが高いこと、そして、限定的な容量しか持てないことです。
外付け型のメリットは、設置や取り換えが容易なこと、パソコン本体とは独立して保管できるためデータの安全性が向上すること、そして、大量のデータを保存することが可能なことです。デメリットとしては、データ転送速度が遅いこと、電源供給を別途必要とすること、そして、パソコン本体から離れた場所に設置する必要があるためスペースを必要とすることが挙げられます。
以上のように、両者はそれぞれメリットとデメリットを持ち、使用する目的や環境によって選択するべきタイプが変わります。
キャプチャボードとフレームグラバーの違い
フレームグラバーもキャプチャボードと同じく映像をパソコンに取り込むためのハードウェアであり、共通する役割は映像をデジタル化してくれる点です。
キャプチャボードは、DVDプレーヤーやビデオカメラなど、普段生活でよく見かける機器から映像を取り込みます。アナログ映像信号をデジタル化してパソコンに送る役目を果たしています。
フレームグラバーは、産業用カメラなどからデジタル映像をパソコンのメモリに取り込むハードウェアで、デジタルIF規格に対応しているものです。特に高速や高精度な映像処理が必要なときに活躍します。
参考サイト:Euresys – フレームグラバー
それぞれの違いは、扱う映像信号の種類や形式です。キャプチャボードはアナログ、フレームグラバーはデジタルを扱うんですね。これにより用途も変わります。
キャプチャボードはテレビやビデオカメラなどの一般的な映像機器から映像をパソコンに取り込むときに使用されます。一方、フレームグラバーはより専門的な医療画像分析や工業用途など、精度と速度が求められる場面で必要とされます。
どちらを使うべきかは、その目的や状況によります。一般的な映像機器からパソコンに映像を取り込む場合はキャプチャボード、高精度や高速な映像処理が必要な場合はフレームグラバーといった具体的な使い分けが考えられます。それぞれの特性を理解し、適切な用途で使うことが重要です。
キャプチャボードの歴史と進化
キャプチャボードがどのように発展し、そのテクノロジーがどのように進化したのでしょうか。これまでの歴史と進化の変遷を見てみましょう。

映像の変遷とキャプチャボードの誕生
昔のパソコンには、映像を出力するためのビデオカードがありました。このビデオカードが、我々が今日知るキャプチャボードの起源となるものです。
当初、ビデオカードは映像を出力するだけの機能を持っていましたが、その後、映像をパソコンに取り込むことができるようになり、この技術の進歩により、キャプチャボードが誕生しました。初期のキャプチャボードはアナログ信号のみを取り込むことができましたが、時代とともにデジタル信号も扱えるように進化しました。
さまざまな用途への拡大
キャプチャボードは、その利用方法が多岐にわたる点でも注目されています。
ゲームの画面をパソコンに映し出すことができ、また、ゲームのプレイを録画して動画を作ったり、ゲームのライブ配信を行ったりすることも可能です。ゲームを楽しむだけでなく、自分のプレイを他人と共有するための重要なツールとなっています。
また、近年ではキャプチャボードなしでもゲームの録画が可能となる新しい製品、いわゆるゲームレコーダーも登場しています。これにより、パソコンがなくても、簡単にゲームの録画ができるようになりました。ただし、これらの製品でも、録画した動画を保存するためのストレージは必要となります。ある意味でキャプチャボードの進化形態ともいえるでしょう。
キャプチャボードの主な用途
キャプチャボードは一般的に以下の用途で使われます。
映像の録画と保存
キャプチャボードが一番よく使われる機能として、テレビやビデオカメラからの映像をパソコン上に録画するというものがあります。あなたのお気に入りの番組や自己撮影したビデオフッテージをデジタル化し後で何度でも再生したり、録画した映像はパソコン上で自由に編集したりできる形です。これにより、自分だけの映像作品を制作することが可能になるでしょう。
ゲームの楽しみ方の拡張
キャプチャボードはゲーム機やDVDプレーヤーからの映像をパソコンに表示できるという機能もあります。この機能を使えば大きなパソコンのモニターでゲームを楽しむことができるはずです。さらに、これを利用してゲームのプレイ状況を録画し、実況プレイやライブ配信をすることが可能になります。これは、ゲームをただ楽しむだけでなく、自分のプレイスタイルを共有し、他の人と一緒に楽しむための手段ともなるでしょう。
パソコン画面の共有
キャプチャボードはパソコンの画面を別のパソコンやテレビに出力できるという機能も持っています。これは、プレゼンテーションや教育の場面で非常に便利です。例えば、複数人でパソコンの画面を見る場合や、大きなスクリーンでパソコンの画面を表示したい場合などに役立ちます。情報を視覚的に伝えることが容易になり、理解度を向上させることができ。
キャプチャボードの選び方
ここではキャプチャボードを選ぶ際のポイントを説明しましょう。

入力端子
例えば、HDMIやDVIなどが代表的な入力端子となり、これらが接続する機器との関係性を決定します。それぞれの端子には特性があり、HDMIが高画質信号の送信に対応しているのに対し、DVIでは音声信号の送信が不可能です。同時に、端子の数も重要な要素となり、何個の機器を一緒に接続できるかを左右します。自身の使用状況に応じて、最適な端子の種類とその数を選択することが必要です。
出力端子
出力端子はUSBやPCIeといった種類があり、パソコンとの接続方法やデータ転送速度に大きな影響を与えます。USB端子は主に外付けのキャプチャボードで利用されますが、その一方でPCIe端子は内蔵型のキャプチャボードに使われることが多いです。またUSBとPCIeでは転送速度に大きな差があります。比べるとUSBの方が遅めの転送速度を持つ傾向にあるため、映像の遅延や画質の劣化を招く可能性があることを覚えておく必要があります。自分のパソコンの互換性や求める性能を基に出力端子の種類と数を選びましょう。
解像度とフレームレート
キャプチャボードの映像品質については、解像度とフレームレートという二つの要素で判断します。解像度は画面の細かさを表す指標で、フレームレートは映像の滑らかさを示すものです。具体的には、「1080p」という解像度は1920×1080ピクセルの画面を、そして「60fps」というフレームレートは1秒間に60回画面が更新されることを意味します。これらの数値が高ければ高いほど、映像品質は良くなりますが、その分データ量も増加します。それゆえに、自分の要求する画質と環境を考え、解像度とフレームレートを決めると良いでしょう。
価格と評判
予算やコストパフォーマンスを考慮する上で、価格は無視できません。また評判は、使用感や信頼性を伺う一つの手がかりとなります。これらはインターネットや雑誌などで比較検討することが可能です。自身の予算を考えつつ、そのなかで評価が高い製品を探すことで、自分にぴったりのキャプチャボードを見つけやすくなるでしょう。
まとめ
キャプチャボードを選ぶうえでまず考えるべきは、”端子”の進化です。入力端子や出力端子がなければ我々のスマートフォンやパソコンは、ただの箱にすぎません。それぞれが具体的な役割を持ち、我々のデジタル生活を円滑に繋げています。
また、映像の品質を左右する解像度とフレームレート。これらも技術の進化とともに飛躍的に向上しています。その結果、より鮮明で滑らかな映像を楽しむことができ、まるで現実の世界にいるかのような体験を可能にしています。
このようなキャプチャボードの進化は、我々の生活をより便利で豊かにするだけでなく、新たな可能性を切り開いています。これからも技術は進化を続け、我々の生活をより良く、より楽しくすることでしょう。