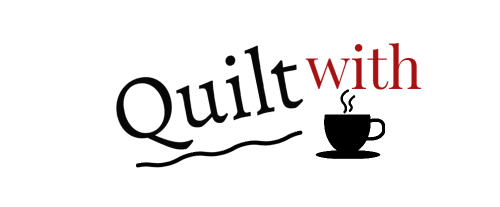求人募集に、「パート」「アルバイト」などの表記を見かけることがあります。しかし、具体的にどのような違いがあるのか説明できない方も多いはずです。今回は、社会保険の加入条件や税金控除などパートとアルバイトの違いについて解説します。
パートとアルバイトの違い
パートとアルバイトには法的な違いはありません。しかし、一般的には使い分けられているので、違いを正しく理解しておくことが大切です。パートとアルバイトの違いを詳しく確認していきましょう。
パートとアルバイトに法的な違いはない
パートとアルバイトは、法律上の区分が明確に定められているわけではありません。パートとは、短時間労働者を指します。正社員はフルタイム勤務が一般的であるのに対し、パートは日・週・月単位で稼働時間を減らして働くのが特徴です。
アルバイトは、パート同様に短時間勤務を指します。どちらも法律上の区分はなく、パートタイム労働者です。パートタイム労働者とは、所定労働時間が正規の労働時間よりも短い人を指します。逆に、正社員のように労働時間通りに働く場合はフルタイム労働者と呼ばれます。
雇用形態で呼び分けられているのではなく、働く時間の長さで区分されるのが特徴です。パート・アルバイトだけでなく、契約社員や派遣社員もパートタイム労働者に含まれます。
使い分けられるようになった背景
法的な違いがないパートとアルバイトですが、慣習的に使い分けられてきました。一般的には、パートは主婦や主夫、アルバイトは学生やフリーターと捉えている方が多いでしょう。このようなイメージが強いのは、語源が影響しているといわれています。
パートの語源は、英語の「part timer」です。主婦が平日の空き時間を活用して働くようになり、これらの労働者を略してパートと呼ばれるようになりました。アルバイトの語源は、ドイツ語の「arbeit」です。生活費を稼ぐために働く学生やフリーターなどの若者をアルバイトと呼んだことから、呼称が定着したと考えられています。
ただし使い分けの方法はケースによって違います。たとえばジョブズゴーの長野県安曇野市の求人・転職情報ページでは、よく「アルバイト」と呼ばれる範囲の求人も「パート」に含めて掲載しています。サイトによってこのカテゴリー分けは変わるため、求人情報を探す際には注意が必要です。
パートとアルバイト【社会保険の加入条件】
社会保険の加入は正社員にのみ与えられた特権だと考える方もいますが、パートとアルバイトでも勤務状況によっては社会保険への加入が可能です。 たとえば、家族の社会保険の扶養に入っている場合、社会保険の加入条件を満たすと、家族の扶養から外れて保険料を自分で支払うことになります。
社会保険への加入条件は、パートとアルバイトでも変わりません。しかし、2022年10月から従業員数101人以上の企業で働くパートやアルバイトの方にも加入対象が拡大されています。社会保険への加入条件は、以下のすべてを満たす人が対象です。
- 正社員の3/4以上勤務している
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
参考元:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入により手厚い保障が受けられます。」
1年で106万円・130万円以上の勤務
パートとアルバイトは年収が一定の額を超えると家族や配偶者の扶養から自動的に外れ、勤務先の社会保険へ加入しなければいけません。一定の額とは、106万円です。ただし、2022年10月に社会保険制度が改正され、社会保険加入対象となるパートやアルバイトの範囲が拡大されています。
改正後に対象になるのは、従業員数101人以上500人未満の企業です。これまで年収130万円まで社会保険の加入義務はありませんでした。しかし、法改正後は年収が106万円を超えると、自分で社会保険に加入する必要があります。2024年10月からは従業員数51人以上の企業も対象になる予定です。
参考元:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
パートとアルバイト【税金控除】
社会保険と同様に押さえておきたいのが、税金控除です。基本的に税金控除は雇用形態に関係なく、パートとアルバイトで得た収入の総額で決まります。主な税金控除は、以下のとおりです。
- 所得税・住民税控除
- 勤労学生控除
- 配偶者特別控除
- 扶養者の税金控除
所得税・住民税控除
パートやアルバイトで稼いだ給与に対して所得税と住民税の税金がかかります。ただし、所得税は年収103万円以下であれば発生しません。住民税には、均等割と所得割の2種類があります。
均等割は、前年の所得金額にかかわらず、一定の所得がある人全員に均等に負担を求める税です。一方、所得割は前年の所得金額に応じて負担する税になります。
勤労学生控除
勤労学生控除とは、働きながら学校に通う学生の税負担を軽減する制度です。一定の条件を満たした者は、所得から一定額が差し引かれる所得控除の一種です。所得税は27万円、住民税は26万円が稼いだお金から差し引かれます。
ただし、給与が103万円を超えると、扶養者の扶養控除の対象から外れて納める税金が増える場合があるので要注意です。
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除が適用されないときに、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除です。たとえば、所得300万円で配偶者控除38万円分が適用されると所得税が3.8万円安くなります。
ただし、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。会社に勤める人は年末調整時に、個人事業主は確定申告のときに申請します。
パートとアルバイト【有給休暇】
有給休暇は、正社員の特権だと考える方もいるかもしれません。しかし、パートやアルバイトでも一定の条件を満たしていれば有給休暇を取得できます。パートやアルバイトが有給休暇を取得できる条件は、以下のとおりです。
- 勤務してから半年以上経過している
- 所定労働日の8割以上出勤している
1年で取得できる有給休暇は、労働日数や労働時間、継続勤務日数で変わります。基本的に勤続年数が長いほど付与される日数が増えます。ただし、有給休暇の時効は発生から2年間です。2年を過ぎると自然消滅します。
参考元:厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。]
パートとアルバイト【残業手当】
パートやアルバイトでも、所定労働時間を超える場合は残業代が支給されます。法定労働時間は、「1日8時間、週40時間以内」です。この法定労働時間を超えた分は残業になり、通常の時間給に25%以上割り増しした額の残業代が支払われます。
1ヶ月に60時間を超えた場合、割増率はさらに引き上げられ、残業代は50%以上の割増し金額です。残業代のほかにも、休日手当や深夜手当などが支給される場合があります。休日手当や深夜手当は残業代と同じく、割増しされた手当が支給されます。
まとめ
パートやアルバイトは、法律上の区分が明確に定められているわけではありません。どちらも所定労働時間が正規の労働時間よりも短い労働者を指す「パートタイム労働者」に区分されます。ただし、正社員と同じように、社会保険の加入条件や税金控除、有給休暇、残業手当を受けられます。