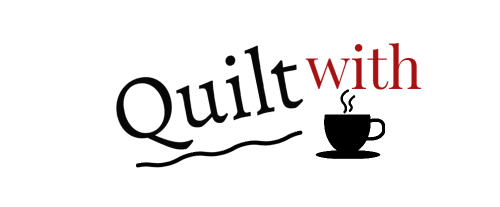仕訳伝票は、経理作業に使われるツールであり、企業の財務状態を正確に把握し、スムーズな経理作業を進める上で絶対に欠かせないものです。財務データの精度を高め、正確な経営判断をおこなううえでも重要となります。
本記事では、仕訳伝票の基本的な役割を理解するうえで押さえたい伝票の基本として、さまざまな伝票の種類や具体的な作成方法、仕訳伝票の注意点を解説します。
仕訳伝票とは
仕訳伝票は、取引の内容を総勘定元帳に転記する前に、個々の取引単位で仕訳を行うためのものです。仕訳を振り替える作業も一緒に行われることから、振替伝票という名前もあります。
記入は借方と貸方の欄に勘定科目や金額を記載し、貸借対照表や損益計算書に準じて行うのが一般的です。日付や取引の内容も必ず記入します。いわば会計の基礎となるもので、個々の取引を時系列で記録する仕訳帳と連動して使われます。
請求書と仕訳伝票の違いは、金銭のやり取りの有無にあります。伝票の場合は商品やサービスの結果として金銭の動きが発生した時点で発行する形です。請求書の場合は提供後に代金を請求するためのもので、金銭のやり取りはまだ発生していない段階で発行します。
伝票の種類
伝票は入金、出金、振替、仕入、売上の5つの種を使い分けることで、スムーズな会計処理が可能になります。上部に番号、取引の年月日、入金先などを記入し、下部に合計金額を記載するのはどれも共通です。適切に使えば日々の取引の記録がより正確になり、信頼性のある会計情報を提供できるでしょう。
それぞれの特徴と利用状況に焦点を当てて理解することで、どれを選択するべきかの方針を立てやすくなります。ここでは、それぞれの種類について紹介しましょう。
入金伝票
入金伝票は、現金が入金された際に利用するもので、「現金入金があった」ことを示すためのものです。その特徴として赤色の線が印刷されており、ひと目でそうであると識別することが可能です。総勘定元帳への転記が必要な場合、現金の項目は常に借方に記録され、貸方の対象項目だけを記入するという形式が取られます。
出金伝票
出金伝票は現金の出金があった際に利用するものです。交通費や書籍購入代などの際に記入するもので、総勘定元帳に転記する際は、常に貸方に現金が記載されるようになっており、借方のもののみを記入する形式になっています。
振替伝票
現金以外の取引を行う際に必要となるものです。一般的な入金や出金伝票とは異なり、借方と貸方の勘定科目が取引ごとに変動するため、両方記録します。通常は左側に借方科目を、右側に貸方科目を記載し、それぞれの取引内容に合わせて詳細を書き込みます。1伝票制では、振替伝票と仕訳伝票を同じものとして扱う点も覚えておきましょう。
仕入伝票
5伝票制を採用している伝票式会計で必要とされるものです。これは仕入れ取引の記録に特化しており、借方には「仕入」、貸方には「買掛金」という勘定科目が固定されています。たとえ商品を現金で購入していたとしても、まず買掛金として処理し、その後すぐに現金での決済が行われたと記録するのが一般的なやり方です。
売上伝票
5伝票制の中で伝票式会計において使用されるもので、売上の取引を明確に記録するために活用されます。特定の勘定科目が設定されており、総勘定元帳への転記時には貸方に売上、借方に売掛金が記入される方式です。たとえ商品の販売に際し、現金で受け取った場合でも、取引の透明性を保つために一度は売掛金での販売として処理し、その後で現金の回収として記録するのが一般的な手順となります。
伝票制の特徴
伝票制には主に3種類あります。その種類によって企業の運営効率と業績に大きく影響するため、それぞれの特性を理解し、適切な選択を行う必要があるでしょう。

1伝票制の特徴
会計の基本となるもので、借方や貸方の勘定科目と金額など、取引内容を仕訳伝票の一種類で記入する方法です。現金取引であっても入金や出金の起票はなく、すべてが借方・貸方の記入に集約されます。デメリットとしては仕訳が複雑になることと、集計の手間がかかるため効率が悪いとされるため、あまり採用されることは少ないのが現実です。
3伝票制の特徴
入金、出金、振替の3種類を使い、現金の取り扱い効率を高めます。入金と出金の伝票に分けて記入するため、総勘定元帳への転記の手間を削減可能です。飲食店や小売店舗など、現金取引が主の業種でよく採用されます。
5伝票制の特徴
入金、出金、振替の伝票に加え、仕入と売上の伝票の計5種類を用います。仕入と売上の伝票を別に起票することで、集計作業の手間を削減。主に掛け取引が主の業種でよく採用され、集計の効率化が図られます。
伝票を作る方法
伝票を作る方法としては、手書きやエクセルを用いた方法、外部に委託する方法、OCR技術を活用する方法、取引先から提供される請求データなど、様々な手法が存在します。それぞれの方法での特徴と注意点について詳しくみていきましょう。
手書きによる作成
まずは手書きで作成してみるというのは、基本的な知識を理解する観点でおすすめします。パソコンを利用できない場合にも手軽に使用が可能です。しかし、手書きでは改ざんの危険があります。消えないペンを利用し、修正時は二重線で消し、訂正印を押してから正しい内容を記入するなど、基本のルールを徹底しましょう。
エクセルによる作成
エクセルによる作成は、紙の伝票が溜まらず、データ共有も可能で管理が容易です。ただし、人為的なミスが起こる可能性があるため注意が必要です。また、帳票の枚数が増えるとおびただしいデータ量になります。
外部委託による作成
外部委託することで、業務の負担を軽減し、精度の向上にも寄与します。また専門的なスキルを持った業者に依頼することで、より高い正確性を期待することがでるのです。ただし、注意が必要な点も存在します。外部への委託は経費がかかりますので、コスト管理に慎重であることが必要です。また、外部に頼りすぎると、自社の経費に関連する問題や課題の発見が遅くなる可能性も考えられます。このようなリスクを避けるためにも、外部への依存度を適切に管理し、必要な場合には自社でもチェックを行うなど、バランスの取れた対応が求められます。
OCRによる作成
OCRは印刷された文字をテキストデータ化する技術で、自動化により誤入力を防ぐことが可能です。定型でない伝票の認識が難しい場合もあるため、最近ではAI-OCRも登場しています。
取引先からの請求データによる作成
取引先とのデータやりとりにより、紙やPDFデータを使用して作ることができます。
取引先の理解が必要であるため、請求書の電子化に関して注意しましょう。
仕訳伝票の注意点
仕訳伝票は会計処理の重要な一部で、注意深く取り扱わなければなりません。毎日の業務の中で小さなことかもしれませんが、正確に処理することで、会社全体の信頼性を高めることができます。基本的なチェックポイントを押さえ、正確な会計処理を目指しましょう。
保存期間
保存には、法人税法や会社法の規定があります。法人税法では取引に関する帳簿としての保存期間は7年、会社法では10年と定められています。保存する文書にはいくつかの要件があり、重複する内容の文書は、原本だけ残し、他は廃棄することが必要です。文書に書き込みがある場合には、保管する文書に転記しなければなりません。さらに、保存の最終期限も記載しておくことと、期限が来た文書の廃棄も忘れずに行いましょう。
処理のミス
重視するポイントとして、貸方と借方の合計が一致しているかどうかの確認が必要です。この一致を確保することが会計の基本となります。勘定科目と金額の間違いは、会計処理において特に重要な部分で、ミスが起きやすい箇所です。時間に追われていても、これらの点については最低限のチェックを忘れずに行うようにしましょう。
摘要の明確さ
摘要の記載内容は第三者が見ても理解できるものでなければなりません。わかりやすく、正確に記載することが求められます。
まとめ
仕訳伝票は経理に欠かせないツールであり、使い方は多岐にわたります。それぞれの種類に合わせた作成方法があり、注意しなければならない点も多いです。ルールを理解し、実践することで、経理業務の効率と精度を高めることができるでしょう。
経理に関わる方々はもちろん、業務で伝票を扱う可能性がある方は、仕訳伝票についても押さえておくことをお勧めします。